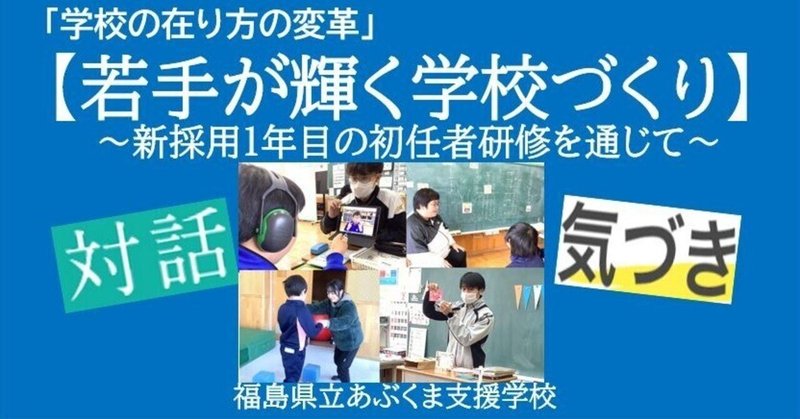
【若手が輝く学校づくり】~新採用一年目の初任者研修を通じて~(福島県・特別支援学校・学校の在り方の変革)
【対談】
令和5年度初任者 (勝又教諭 ・ 石井教諭 ・ 長澤教諭 ・ 冨田教諭)
取材・インタビュー (情報教育部:木谷 俊彦(情報主任)・本田 慎一)

【若手が輝く学校づくり】~初任者研修~
あぶくま支援学校では、令和5年度は4名の初任者が新採用として着任し、1年間の初任者研修に取り組んできました。
※初任者研修は、新たに公立の小・中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の教諭となった新任教員に対して、教育公務員特例法第23条の規定により、現職研修の一環として1年間の研修を実施し、実践的指導力と使命感を養うとともに、幅広い知見の習得を図ることを目的として行われるものです。

1年間の研修を通して、教師としての心構えや学級経営、授業作りのほか、ICTの効果的な活用、生徒指導、進路指導に関することなどについて学ぶとともに、先輩教員との対話を通して、「学びの変革」や「学校の在り方の変革の推進のために求められるもの」などについて考える機会となりました。
採用から1年が過ぎた4名の若手教員に聞きました。
Q1 1年間の初任者研修を通して、自分が変わったと感じることはありますか?
勝又教諭
福島県特別支援教育センター研究発表会において、障がいの当事者の方からお話を聞く機会がありました。それまでは、生徒とのかかわりにおいて、『同じ質問を繰り返ししてくること』や、『年齢不相応な行動』への対応など、迷いながらかかわっていました。しかし、当事者の視点から『答えてもらうことが本人の安心につながる』と教えていただけたことで、本人の思いを受け止めることの大切さに気付き、生徒たちとのかかわり方が変化しました。

冨田教諭
本人の思いを受け止めることの大切さは、私もこの1年間で実感しました。小学部の新1年生として入学した児童とのかかわりにおいて、強いこだわりの行動に対して、児童本人も私もどうしたら良いのか、どのようにすれば生活の豊かさにつながっていくのかが分からず、戸惑っていたことがありました。初任者研修を通して、『生活の豊かさの基盤は、身近な人との信頼関係である』ということを学び、本人の思いを受け止めるために「わかったよ。」と言葉かけをするようにしました。本人の思いを受け止めてきたことで、今では言葉での簡単なやりとりができるようになってきました。信頼関係を丁寧に築く、そのために本人の思いを受け止める言葉がとても大切であるということに気付きました。
長澤教諭
1年間の研修を通して、私は授業の計画の仕方が変わりました。はじめは、自分自身で何とかしようという思いが強く、授業作りに関して悩みがちでしたが、周りの経験豊かな先生方から、たくさんのアイデアやアドバイス等をいただき、助けられる場面が多々ありました。実際に授業を行ってみても、自分一人で考え、準備した授業よりも、チームで考えて準備をした授業の方が、生徒の成長の幅が大きくなることを実感しました。
学級担任のA先生は、多くの先生方の意見やアイデアを聞き、それらを組み合わせていくことがとても上手な先生でした。A先生の前向きさと物腰の柔らかさなど、これから私自身も真似ていきたいと思いました。

石井教諭
私が担当する学級においても、こだわりが強く、自分で決めたことでないと拒否を示す児童もおり、どう学習を提案したらよいのか、本来指導すべき立場である自分自身が困ってしまったことがありました。その時、ある先輩の先生から『困っているのは、その子本人だよね。』との言葉ともらい、児童の行動の背景にある思いを見取ることの重要性に気付き、教師としての見方が変わりました。それからは、その子の好きなことを探り、魔法(言葉やしぐさで行動を促す)をかけたり、BGMを流したりして、気持ちを切り替えるきっかけを探っていきました。それらの継続が、学習へ向かう姿へもつながっていきました。その子と、とことん付き合うということも時には大切なのだとあらためて感じました。
Q2 1年間の初任者研修を終えて、あらためて今思うこと、感じることなどはありますか?
勝又教諭
福島県で最も規模の大きなあぶくま支援学校には、たくさんの専門性や経験をもった先生方がいます。その先生方のお一人お一人が、「子どもたちの学び」についての考えや視点をお持ちです。また、それらは実に多様です。
この1年間で様々な視点や考え方に触れることができました。まだまだ自分の「考え・視点」はもてていませんが、これからも様々な考えに触れながら、子どもたちの成長や学びの充実のためには何が必要なのか、自分には何ができるかを考えていきたいです。

長澤教諭
初任者研修を通し、授業作りから学校運営の仕組みまで、丁寧に御指導いただきました。学校運営についても大切なことが多くあるため、まだまだ理解できていな部分もあると思いますが、次年度以降もしっかり学んでいきたいと思います。
冨田教諭
この1年を通し、子どもたちと思いが通じる瞬間をたくさん経験することができました。これからも子どもたちの成長を支えていきたいと思います。

石井教諭
周囲の先生方や子どもたちの笑顔に支えられ、1年間の研修を終えることができました。百数十名もの教職員が所属する本校では、日々の連絡調整や校務分掌の仕事などについても悩む場面もありましたが、子どもの成長や笑顔のためにこれからも頑張りたいと思います。

Q3 特別支援学校の教員になってよかったと感じることはありますか?
勝又教諭
教師は、生徒の成長を一緒に共有できる素敵な仕事です。当初、私がかかわり方や支援の在り方について悩んでいた生徒から、「先生一緒にやろう。」と誘ってきてくれた瞬間は何より嬉しかったです。これからも忘れることはないと思います。
長澤教諭
教師は、常に学び続けることができる仕事です。様々な知識や経験、専門性をもった先生方と一緒に働くことで、児童生徒のみならず、自分自身も人間としてより成長できていると感じます。
冨田教諭
教師は、子どもの思いに寄り添う仕事です。子どもと同じものを見て笑ったり、言葉を交わしたり、子どもが見たりしている世界を一緒に共有できたときは幸せです。
石井教諭
教師には、場面や状況から、気持ちや背景などを想像する力が求められます。一人一人の子どもたちの声や表情を読み取り、思いを共有できたときにとてもやりがいを感じることができます。
【情報教育部より】(木谷・本田)
学校の情報を管理・運用する役割として、学校の在り方の変革や教育のDX化推進に向けて日々取り組んでいます。また、校内の各部が連携を図った先進的な情報モラル教育にも取り組んでいるところです。
今後も、学校の在り方の改革、学びの変革に向けた取り組みについて、取材・掲載していきます。(企画・木谷)

